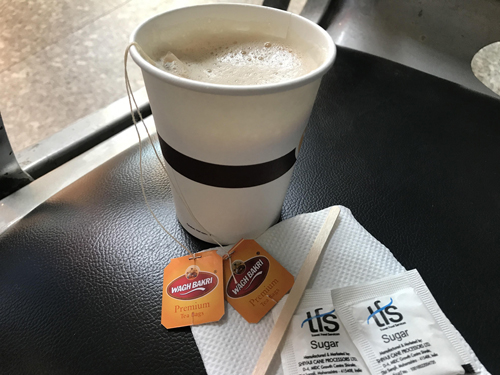shinowazuri– Author –
shinowazuri
-

サンスアティーエステイト(Sangsua T.E.)③発酵機
サンスアティーエステイトは2017年設立ということですが、前回一度来ていると思い出したのは、不思議な装置があったから(オーナーが変わって名前が変わったかもと)。前回はお掃除中で何に使うものかわからなかったけれど、今回その謎がとけました^^ こ... -

サンスア茶園(Sangsua T.E.)②萎凋室の3本ライン
四面ある萎凋室に広げられるその日の茶葉量は一面3000kg。萎凋槽の壁には赤、黄、白のラインがひかれています。赤のラインまで積んだ茶葉は攪拌をします。白のライン(高さ10cm)まで積んだ茶葉は攪拌は不要です。白のラインまでしか積まないのはどんな葉... -

サンスア茶園(Sangsua T.E.)①茶摘み人の一日
サンスア茶園は2017年に設立したアッサムの中では規模小さめの茶園、1200人ほどのスタッフが働いています。その中の大半1000人がプラッカー(茶摘み人)で構成されており、この時期(季節によってノルマが違います)一人一日30kgのノルマでお仕事していま... -

茶園ロードを行く@ジョルハット
北東インドのブラマプトラ河の両岸に広がるアッサム平原は、世界有数の多雨地帯であり、世界最大の紅茶産地です。アッサム州ジョルハットはトクライリサーチ研究所(Toklai Reserch Institute)もある茶園が集中している地域。様々なティーエステイトの茶... -

ネータージー・スバース・チャンドラ・ボース国際空港
ネータージー・スバース・チャンドラ・ボース国際空港(Netaji Subhash Chandra Bose International Airport)、とても長い空港名。簡単にチャンドラ空港と言われているとか。インドの西ベンガル州コルカタにある国際空港の名前です。コルカタからアッサム... -

コルカタの10月はドゥルガー・プージャ
インド人の多くが進行するヒンドゥー教。ヒンドゥー教の神様はいっぱいいらっしゃり、それぞれの神様を礼拝するPUJA(プージャ)というお祭りが行われます。旅先の東インドの大都市コルカタでプジャの新聞記事を見て調べれば、10月にはドゥルガー・プージ... -

キルフェボン、秋のお茶タルト
日本の春夏秋冬、旬のフルーツがキラキラ宝石をてんこ盛りにしたようなキレイなタルトがショーケースに並んでいるのを見るも楽しいタルト専門店キルフェボンが生まれたのは静岡。一度はイートインしてみたい静岡市の本店はもちろん行列のできる人気店。秋... -

潟端茶@佐渡
佐渡に茶ありと、その名が佐渡茶の代名詞になったのが江戸時代享保年間の末期からお茶作りが盛んになった潟端茶です。佐渡島の交通の門戸両津港に近い加茂湖周辺潟端は、茶粥(茶げえ)で有名な地区で、家でつくった番茶を釜か鍋にいれて煮て、そこに前の... -

都文化とともに妙なる金の島に渡った茶粥@佐渡
国生神話によると日本国を造った神イザナギとイザナミが七番目に生み、『古事記』の頃から佐渡と呼ばれた島は、島という性質上古の伝統文化が守られ存在しているのでしょうか?それは、承久の乱に敗れ21年間を島で過ごし生涯を終えた順徳上皇なのか、幕府... -

佐渡の茶畑 その2
佐渡に茶樹が伝えられたのはいつなのでしょうか? 佐渡では、茶生産以前に茶粥文化が古の昔より存在し、現在も一部地域の食習慣として根付いています。文献をあたれば、室町時代、吉井の大聖院の文書には“茶がゆの神事”が行われていました。佐和田の真光寺...